もうすぐ年の瀬。クリスマスが過ぎると、一気に街はお正月モードに切り替わりますよね。でも、「お正月の準備っていつから始めるもの?」「何をすればいいの?」と、ふと立ち止まってしまうことありませんか?そんなときに知っておきたいのが「正月事始め(しょうがつことはじめ)」という言葉。
昔ながらの日本の暮らしには、「新しい年をどう迎えるか」という丁寧な心配りが根付いています。「正月事始め」はただの掃除や買い出しじゃない。そこには、家族の健康や幸せを願う“想い”が込められているんです。
この記事では、そんな「正月事始め」の由来や意味から、現代の暮らしに合った取り入れ方までを、わかりやすく、そしてちょっぴり心がほっこりするような視点でお届けします。年末年始を、もっと気持ちよく過ごしたいあなたへ——。
正月事始めとは何か?
正月事始めの意味と由来
「正月事始め」は、昔の暦でいうところの「12月13日」に行われる新年準備のスタートのこと。江戸時代には「煤払い(すすはらい)」や「松迎え(まつむかえ)」などの行事がこの日から始まったんです。つまり、この日から「年神様」を迎える準備を本格的に始めるのが習わしだったんですね。
「年神様」は新年にやってきて、私たちに幸せや実りをもたらしてくれる神様。だからこそ、神様を迎える“家”を綺麗に整え、飾り付けをし、気持ちも新たに年越しを迎える。この一連の流れが「正月事始め」なんです。
煤払いと松迎えの意味
「煤払い」は、家のほこりや汚れを払って清める行事。今でいう“大掃除”のルーツですね。ただ掃除するだけじゃなく、「一年分の厄や穢れ(けがれ)を落とす」という、心の意味合いも含まれていました。
「松迎え」は、門松に使う松を山から取ってくる習わしのこと。今ではお花屋さんやスーパーで買うことが多いですが、昔は自ら山に入り、神様をお迎えする木を選んでいたんですね。その姿には、日本人の自然との共生の精神が表れていて、ちょっと胸が熱くなります。
正月事始めにやることリスト
① 家の大掃除
まずはやっぱり掃除から。特に、神棚や仏壇がある家庭ではこのタイミングで丁寧にお清めをします。キッチンや玄関、水回りなど、「気」の流れに関わる場所を中心に、スッキリさせると気分もリフレッシュ。
ポイントは、「完璧にやろう」としすぎないこと。1日で全部やるのは大変なので、エリアごとに小分けにして数日かけてやるのがおすすめです。
② 正月飾りの準備
門松・しめ縄・鏡餅などの正月飾りもこの時期から準備を始めるのが理想。飾りは28日までには済ませておくのが縁起が良いとされてます(29日は「苦を待つ」、31日は「一夜飾り」で避けられます)。
飾りに込められた意味を知ると、なんだか毎年の作業が少し楽しく感じられるんですよね。たとえば、門松は年神様の目印、しめ縄は結界、鏡餅は神様の宿る場所…などなど。

③ おせちや年賀状の準備
忙しない年末に向けて、料理の仕込みや年賀状の作成もこの時期から始めると安心。最近は「手作りは一部だけで、あとは市販品でOK」という方も増えてきています。大切なのは“形”よりも、“気持ち”です。
忙しい現代でもできる!ゆるっと正月事始め
「心の煤払い」をしてみよう
掃除は苦手…という方も、「心の掃除」から始めてみませんか?今年の振り返りをして、感謝の気持ちを言葉にしてみたり、手帳やスマホのメモに「今年嬉しかったこと」を書き出してみるだけでも気持ちが整います。
心が整うと、自然と行動もスムーズになるから不思議です。まずは自分に優しく、「よくがんばったね」と声をかけてあげるのも、立派な“事始め”。
家族で過ごす年末のひととき
昔の人は、正月事始めを通して“家族の絆”を確認していたのかもしれません。掃除を一緒にする、飾りつけを一緒に考える、おせちを一緒に味見する——そんなちょっとした時間が、子どもにとっても心に残る年末の思い出になるはず。
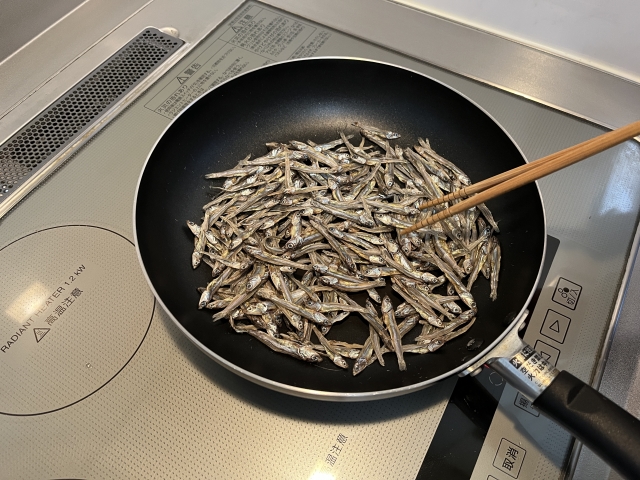
「みんなで新年を迎える準備をする」って、すごく素敵なこと。子どもがまだ小さいなら、紙でミニ門松を作ったり、年賀状に手形スタンプを押したりするのもおすすめ。
正月事始めをもっと楽しむアイデア
昔の風習をゆるく取り入れる
正月事始めって、なんだか堅苦しい? でもそんなことないんです。たとえば「松迎え」にならって、近所の公園を家族で散歩して、拾った松ぼっくりを飾りにするだけでもOK。
昔の行事を“ゆるく今風に”楽しむことが、逆にいまの暮らしにはぴったりかもしれません。
お正月準備をSNSでシェア
年末の準備風景や、我が家流の飾りつけをSNSで発信する人も増えています。「他の家庭ってどんなふうにしてるんだろう?」という参考にもなるし、「私もやってみようかな」と前向きな気持ちにもなれるから不思議。
誰かと気持ちを共有すること自体が、立派な「事始め」なのかも。
まとめ
「正月事始め」は、ただの“年末のルーティン”ではなく、新しい年を気持ちよく迎えるための「心と暮らしのチューニング」みたいなもの。そこには、目に見えないけれど確かにある、日本人の丁寧な暮らしの美学が息づいています。
忙しい毎日だからこそ、ほんの少し立ち止まって、年神様を迎える準備をしてみる。掃除も、飾りつけも、おせち作りも、どれも「ありがとう」と「ようこそ」の気持ちを伝えるためのものなんだと思うと、ちょっと背筋が伸びる気がしませんか?
完璧じゃなくていい。できることから、気持ちのこもった年末時間を重ねていきましょう。今年の「正月事始め」が、あなたにとってあたたかく意味のあるものになりますように。
よくある質問(FAQ)
正月事始めって、いつからいつまで?
正式には12月13日から準備を始めますが、実際にはその週末やクリスマス後から始める家庭も多いです。
正月飾りはいつまでに出せばいいの?
一般的には28日までに飾るのが良いとされています。29日(「苦を待つ」)と31日(「一夜飾り」)は避けましょう。
大掃除はどこから始めるといい?
「玄関」「キッチン」「水回り」がおすすめ。運気や清浄さに関わる場所から手をつけると、効果的だと言われています。


